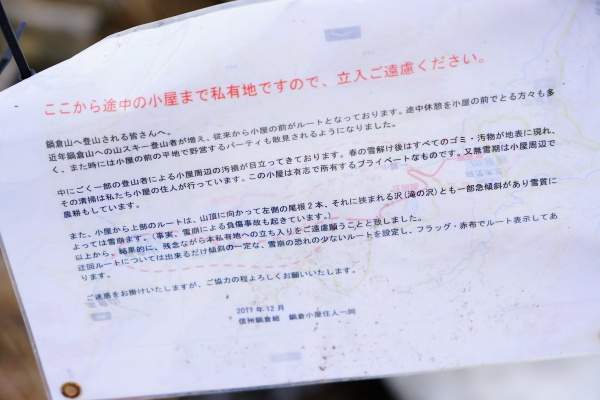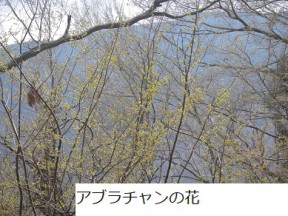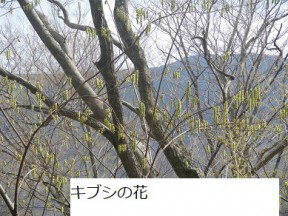2018-4-21 燧ケ岳 山スキー
春の山スキーに出陣。
今回は燧ケ岳。
御池まで開通するのは例年5月の連休からなので、
ふもとの七入から登れるところまでいってみるつもりだった。
ボク的には途中のブナ平で残雪のブナの森が撮れれば満足、ってこともあった。
ところが金曜日の夜中に現地に行ってみると七入のゲートが開いていた。
道路には雪は皆無で、結局御池の駐車場まで行けちゃったという感じ。
翌日民宿のご主人に聞いたところ、われわれが通った日の午後に開通したらしい。
これはラッキー。
開通情報はweb上に出てなかったからか、御池駐車場はボクたちが一番乗りだった。
仮眠から起きるとクルマは2、3台。
早くもボーダーたちが出発していた。
支度しているとポツポツとスキーヤーが集まってきた。
登り口で支度中の方に話を聞くと、会津駒に行こうとしたがあまりの雪の少なさにこちらに来たとのこと。
今年の雪は少ない。
 朝の御池駐車場 |
 |
夏ルートに沿ってスタート。
快晴の青空にギラギラと太陽が昇ってきた。
暑い。最初の登りでハードシェルを脱いだ。
最初の急登を越えると広沢田代だ。
 登高開始 |
 快晴 |
 |
 |
 背後には会津駒がクッキリ |
 |
 |
 広沢田代 |
そこを越えると一気に視界が開けた。
眼下には熊沢田代が広がり、その先には名山の燧ケ岳が貫録の姿を見せていた。
熊沢田代のベンチは雪から出ていてそこまでわずかな下り斜面。
みんながシールでおりるのを横目に、ボクたちはシールをはずして少しばかりの滑走を楽しんだ。
 |
 |
 広沢田代から登ってきた |
 ダケカンバの樹 |
 燧ヶ岳がみえてきた |
 絶景です |
 |
雄大さがわかる。
木道で休んでいると多くのスキーヤーが湿原のフチを登ってきた。
このルートは細かく調べてなかったが、どうやら彼ら、われわれが登った急坂を巻いているようだ。
 |
暑さはあいかわらず。
アンダーシャツ1枚で十分だ。
森林限界を過ぎて胸突き八丁を懸命に登った。
最後にトラバースすると俎ぐらの直下に出た。
 山頂下の急坂を登る |
 頂上をめざすスキーヤー |
 青天に向かって |
頂上には多くのスキーヤーが登頂を祝っていた。
とにかく風のない穏やかな頂上だった。
ハードシェルをはおる必要はない。
眼下にはぐるりと尾瀬沼、尾瀬ヶ原と至仏山、双耳峰の柴安ぐら、会津駒が岳が一望できた。
あまりの快適さに1時間ほどのんびりした。
 |
 至仏山と尾瀬ケ原 |
 |
 柴安ぐらの向うに至仏山 |
 |
滑走開始。
頂上直下のオープンバーンをショートターンで快適に滑った。
熊代田代に向かってトラバースしながらいくつかの沢筋を下る。
下へ行くほどストップ雪状態。
ターンができない。
気温が上がりすぎて快適なのは頂上直下ぐらいだった。
あとはスキーが滑らず、若干苦痛気味に。
熊沢田代の東側の急斜面を滑って東ノ田代の雪原で休憩。
あまりの暑さにテルモスのお湯に雪を溶かして冷水にした。
 山頂直下はサイコー! |
 |
 会津駒をバックに |
 |
途中、深い沢やブッシュで難儀しながらもなんとか突破。
広沢田代東面のきれいなブナ林となった。
けっこうな巨木もありなかなかのブナ林だ。
西側には沈まんとする太陽がのぞき光と影を演出していた。
高度調整ミスから、最後は若干登りながら無事駐車場に戻った。
 |
 |
下山後は温泉、そして民宿の山人料理に舌鼓を打った。